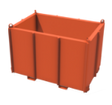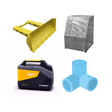フォークリフトの名称や用語を正しく理解することは、安全かつ効率的な荷役作業に欠かせません。
本記事では、フォークリフトの基本構造や各部の役割をわかりやすく解説します。
フォークリフトを初めて扱う方でも、しっかりとポイントを押さえて安全に運用できるようにまとめました。
フォークリフトの基本構造と特徴
フォークリフトを理解する上で、まずは全体の構造や特徴をつかむことが大切です。
フォークリフトには、大きくカウンターフォークリフトとリーチフォークリフトの2種類があります。カウンターフォークリフトは車体後部に重り(カウンターウェイト)を搭載し、荷物を持ち上げる際のバランスを取りやすい構造になっています。一方、リーチフォークリフトは、小回りの良さが特徴で、狭い倉庫内でも効率的に作業することが可能です。いずれもマストやフォークなどの主要部品を備え、荷物の昇降や移動を円滑に行います。
フォークリフトの運転は主に後輪を操舵輪とするため、通常の自動車とは異なる感覚でハンドル操作を行う必要があります。また、座って運転するタイプと立って運転するタイプがあり、作業環境に応じて選択が可能です。操作性や作業スペースに合わせた機種選びが、効率と安全性の向上につながります。
カウンターフォークリフトの構造
カウンターフォークリフトの最大の特徴は、車体後部に備わったカウンターウェイトです。荷物を持ち上げる際に重心のバランスを保つことで、安定感のある作業が可能になります。また、一般的にはエンジンを搭載したものが多く、屋外や重量物の取り扱いに適しています。駆動輪を前輪に備えることでパワフルな走行性能を発揮し、さまざまな現場で活躍します。
リーチフォークリフトの構造
リーチフォークリフトは、高さのあるラックが並ぶ倉庫でよく使用されるタイプです。立ち乗りスタイルで運転し、後輪で方向をコントロールするだけでなく、前方のフォークが前後にスライドするリーチ機能を持っています。これにより、前進や旋回を最小限に抑えつつ荷物の位置にフォークを近づけることができ、狭い通路でも効率的な荷役が可能です。
フォークリフトの各部名称と役割

フォークリフトを構成する主な部位と、その役割を整理しておきましょう。
フォークリフトは、荷役作業を行うために多彩な部品で構成されています。マストやフォークなどの荷役装置だけでなく、運転者を保護するためのヘッドガードや、バッテリーを搭載するスペースなど、用途や形式によって構造はさまざまです。各部の名称と役割を把握することで、点検や整備に役立つだけでなく、トラブル発生時の状況説明もスムーズに行えます。
名称を正しく理解しておくことは、安全確保にも効果的です。ヘッドガードのように、荷物の落下防止や運転者保護へ直接つながる部品の名称を知らなければ、点検や整備の優先度を見誤ってしまいかねません。適切なメンテナンスと日常点検を行うためにも、各部の名前と機能をしっかり確認しておきましょう。
荷役装置(マスト、フォーク、バックレストなど)
マストはフォークを上下させるためのレールで、内側にインナーマストを持ち、シリンダーの油圧によって昇降が行われます。フォークは荷物を直接持ち上げる部分で、一般的には“ツメ”と呼ばれることも多いです。バックレストはフォーク上に載せた荷物の後方への落下を防ぐ役割を果たし、安全な荷役を支える重要な部品といえます。
運転席(ステアリング、ペダル類、レバー類ほか)
運転席には、ハンドル(ステアリング)やアクセル、ブレーキ、クラッチなどのペダル類、フォークの上下やチルト角度を操作するレバー類が配置されています。カウンターフォークリフトの場合は座って操作し、リーチフォークリフトでは立ったまま操作する形式が一般的です。これらの操作部位の配置を熟知していれば、直感的かつ安全に荷役作業を進めることができます。
車体外部(エンジンルーム、エンジンフードなど)
エンジン式フォークリフトでは、車体外部にエンジンルームがあり、エンジンフードを開けると内部の点検が可能です。冷却装置や排気系統のメンテナンスを行う際には、エンジン周辺の構造を理解しておく必要があります。また、車体後部のカウンターウェイトも外側に取り付けられ、荷物を持ち上げる際の重心バランスを保つ働きを担っています。
車体内部(バッテリー関連、モーターなど)
電動式フォークリフトでは、バッテリーが電力源となり、そのエネルギーをモーターへ供給して駆動や荷役動作が行われます。リーチフォークリフトや小型タイプで広く使われており、排気ガスの心配がないため屋内でも安心して運用できます。バッテリーやモーターの状態を把握するためには、定期的に点検し、充電方法や動作音に注意を払うことが重要です。
主要諸元と構造図の見方

※引用:厚生労働省HP
フォークリフトの仕様を確認する際、主要諸元と構造図を正しく理解する必要があります。
フォークリフトを選定するときやメンテナンスを行う際には、製品の主要諸元を確認することが欠かせません。例えば最大積載量や最大揚高、車体重量、エンジンの排気量などが記載されており、一度に運搬できる荷物の重さやどのくらいの高さまで荷を上げられるかを知る基準になります。こうした数値の把握が作業計画を立てる上で大変重要です。
構造図では、マストやシリンダー、ステアリング系統など、フォークリフト内部のレイアウトを確認できます。メンテナンスを行う際には、どの部品がどこに配置されているのかを理解しておけば、スムーズに点検・修理が進められます。構造図と主要諸元を併せて見る習慣をつけることで、環境や業務内容に最適な機種選定や運用方法を見極めやすくなるでしょう。
主要諸元で押さえておきたい項目
最大積載量はフォークリフトが安全に持ち上げられる荷物の重さを示し、車両の安定性を左右する重要な指標です。さらに最大揚高は、マストが伸びる限界の高さを意味し、高い棚やラックへの荷物の収納が可能かどうかを判断する材料になります。最小旋回半径や全長などのサイズ情報も、狭い倉庫での取り回しを検討する際に見逃せません。
構造図で確認しておきたいポイント
構造図では、マストやフォークの配置だけでなく、油圧シリンダーやチェーン、エンジンやバッテリーの位置まで把握できます。メンテナンス時には、点検すべき部位がどこにあるかを迅速に見つけ出すためにも、構造図を一度じっくりと確認しておくことが大切です。作業上の安全対策を講じるためにも、配管や電気系統の経路を理解して作業に臨みましょう。
フォークリフト用語集

※引用:厚生労働省HP
現場でよく使われるフォークリフト特有の用語を理解しておきましょう。
フォークリフト操作には独特の用語が存在します。操作レバーの名称や油圧動作を表す言葉、安全機能を示すスイッチや装置など、現場では頻繁に飛び交うため、早めに覚えておくとスムーズにコミュニケーションが取れます。特に新人オペレーターは、言葉を正しく認識することで周囲からのアドバイスを円滑に受け取りやすくなります。
業種や会社ごとに異なる呼び方が使われる場合もあるため、使用マニュアルと合わせて現場ごとに確認しておくと安心です。標準的な用語を覚えつつ、現場の習慣に合わせて使い分けをすることで、作業効率やチームワークが一段と向上するでしょう。
荷役操作に関する用語(リフト、チルト、リーチなど)
リフトはマストやフォークを上下させる動作のことで、荷物を持ち上げたり下ろしたりする際に使用されます。チルトはマストを前後に傾ける機能で、荷物が滑り落ちないように角度を調整するのが主な目的です。リーチは、マストやフォークを前後にスライドさせる動作を指し、リーチフォークリフト独特の機能として狭い通路でも荷役しやすくする役割を持ちます。
安全操作に関する用語(非常停止ボタン、プレゼンススイッチなど)
非常停止ボタンは、想定外の事態が発生した際に一時的に動作を停止させるための重要な装置です。プレゼンススイッチは、オペレーターがシートに座っている、または作業位置に立っていることを検知し、未乗車時には操作を無効にする安全機能を担います。これらの用語を理解していれば、万が一のときにも落ち着いて対応でき、安全面を確保しながら作業を続けられます。
フォークリフト各部名称を理解するメリット
部品名称を正確に理解しておくと、点検や故障対応がスムーズになります。
フォークリフトは多くの部品で構成されており、それぞれが連動して初めて円滑な作業を実現します。各部の名称を理解していると、どの箇所を点検・整備すべきかがひと目でわかり、定期的なメンテナンスの精度が向上します。結果として、性能維持や故障の未然防止につながり、安全かつ効率的な荷役が可能になります。
また、オペレーター同士のやり取りや、メカニックに対するトラブル報告も正確に行うことができるため、作業現場でのコミュニケーションが格段にスムーズになります。迅速な対応が求められる現場では、正しい情報伝達がダウンタイムの削減に大きく寄与するでしょう。
点検・整備の正確性が高まる
例えば、リフトチェーンやチルトシリンダといった部品名を正しく把握していれば、定期点検時の確認項目を明確に洗い出すことができます。マスト部分の摩耗やフォークの損傷など、よく起こりうるトラブルも早期発見につながり、故障リスクを低減できるでしょう。結果的に、常に安定した作業環境を維持できるメリットがあります。
故障時の状況説明や指示がスムーズ
フォークリフトに不具合が生じた場合、具体的な部品名を挙げて報告できれば、メカニック側も迅速に修理プランを立てやすくなります。どの部位がどのように異常を起こしているかを正確に伝えられることで、トラブルシューティングの時間を大幅に短縮できるのです。これによりトラブル処理にかかる時間が短縮され、現場の稼働率を落とさずに済みます。
安全意識と作業効率の向上
各部の名称を共有することで、オペレーター同士の情報伝達がスムーズになり、安全対策のレベルをさらに高められます。また、荷役手順や点検手順の共有が正確に行われるため、チーム全体の作業効率が向上し、現場全体のパフォーマンスアップにつながります。豊富な知識と正しい呼称の使用が、万が一のリスクを最小限に抑え、ミスの発生を防ぐことにも寄与します。
フォークリフトの名称を正しく把握して安全かつ効率的な作業を
本記事で紹介した構造や用語を理解し、現場での安全性と作業効率を高めましょう。
フォークリフトの各部名称や基本的な用語を正しく把握しておくことは、現場作業における安全対策の土台となります。オペレーター同士のコミュニケーションが円滑になり、トラブル対応や点検・整備の精度も高まるため、結果的に生産性向上にも寄与します。さまざまな作業現場で欠かせないフォークリフトだからこそ、基礎知識の習得に力を入れ、日々の業務へ活かしていきましょう。