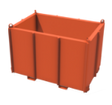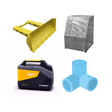車両を動かすために欠かせないバッテリーですが、最近のバッテリーは高性能なものが多く、限界ぎりぎりまで使えるため寿命や不調の兆候が現れにくく、使用していて突然バッテリーがあがってしまうことも少なくありません。
突然のバッテリー上がりを防ぐためには、バッテリーの比重を定期的にチェックすることが大切です。ここでは、フォークリフトバッテリーの比重の測定方法や、バッテリーの交換時期について詳しく紹介します。
目次
バッテリー式フォークリフトの仕組み

バッテリー式フォークリフトは主に鉛蓄電池が使われており、2V電圧のバッテリーセルが直列で複数連結された構造になっており、24ボルト電圧のバッテリーなら12個のセルが、48ボルト電圧のバッテリーなら24個のセルが繋がれています。
各セル内のバッテリー液の比重は、バッテリーのコンディションによって変わります。
※比重とは一言でいうと、「同じ体積での重さが水の何倍なのか?」を示す数値です。
充放電によって比重が変わる
鉛蓄電池のバッテリーセルの内部には、鉛の極板と希硫酸が入っています。希硫酸は低濃度の硫酸の水溶液で、無色透明の液体です。この鉛と希硫酸の化学反応によって、電気を発生させることができるのです。
バッテリー放電時は、鉛と硫酸が結合し硫酸鉛となり、希硫酸は硫酸成分を失うので、放電するほど比重値は低下します。
逆に、充電されると硫酸鉛は鉛へ、液体は希硫酸へと戻ろうとする化学変化が起こります。その際に水が分解され、水素ガスが発生します。
そのため、バッテリーを充電すれば比重値は上昇し、満充電時のバッテリー液の比重は1.28(液温20℃時)になります。
バッテリーの比重が高い原因

バッテリー性能を診断する際の1つの目安に、バッテリー液の比重があります。一般的なフォークリフト用の鉛蓄電池の比重は1.28から1.31の範囲に設定されることが多いため、その範囲内であれば正常値です。
しかし、フォークリフト用のバッテリーの比重は使用する環境や作業の条件に応じて調整されますし、温度の影響も受けます。
暑い夏や寒い時期にバッテリーのトラブルが多いと感じている人も少なくないでしょう。バッテリー液の比重が高すぎても、低すぎても本来の性能を発揮できなくなってしまいます。夏は気温が高いため、バッテリーの液温も高くなります。
バッテリー液の温度が高くなればなるほど、電気を作り出すための化学反応も活発になります。そのため、バッテリー液の比重が下がりやすくなり、希硫酸濃度が薄まって自己放電や劣化が進みやすくなるのです。
冬場はバッテリー比重が低くなる
冬は気温が低いので、バッテリーの液温も当然低くなります。バッテリー液の温度が低くなると、化学反応がしづらくなるため性能も低下します。バッテリー性能が落ちると、放電がうまくできなくなり、エンジンがかかりにくいなどの不具合が出てくるのです。
バッテリー比重が高くなると起こること

バッテリー比重が高いと、化学反応が活発になり自己放電が促進され、バッテリーの劣化が早まります。バッテリーの比重が高くなる原因は、バッテリー液の希硫酸濃度が高いためです。つまり、バッテリーが満充電状態であることが分かります。
バッテリーが劣化すると、各セルの比重にバラつきが生じるため、充電を行ってもエンジンが始動できなくなることがあります。各セルの比重が0.04以上あり、バラつきが大きいものや比重が上がらないものは、バッテリーが寿命になっていることが考えられるでしょう。
ただし、満充電時のバッテリー液の比重が1.28(液温20℃時)よりも高いからといって、すぐにバッテリーの劣化を疑うのは早計です。比重計の精度によって1.3以上になることは一般的です。
バッテリーの劣化を正確に判断しようとするなら、満充電した後に一晩放置して、電圧、比重、CCA、始動時の電圧低下などを見なければいけません。
比重が高いからといってすぐにバッテリー劣化に結びつけて考える必要はないでしょう。
バッテリー比重が低くなると起こること

バッテリー比重が低いと、ライトやポンプなどの機器の動作が不安定になったり、バッテリーの充電が早く失われたりします。また、バッテリーの電力が低下するため、ライトやポンプなどの機器の動作が不安定になることがあるでしょう。さらに、バッテリーの凍結温度も下がります。
バッテリー比重が低くなる原因は、充電が不十分、補充液を入れ過ぎている、電極が劣化している、液温が高温になっている、サルフェーションが発生しているなどが考えられます。
比重値の測定
比重値を測定することによりバッテリーコンディションの概要を判断します。充電しても比重値が極度に低い場合、電極板の物理的な劣化やセルの故障が考えられます。
比重値の測定は、満充電の状態で比重計を使って測定します。比重計はスポイトの中に目盛りのついた棒が入った構造になっています。比重が高い液体をスポイトで吸い込むと、棒が浮き上がります。このときの液面が示している目盛りの位置が比重になります。
比重計でバッテリー液を吸引して測定すると、正常な値であれば液温20℃で1.28±0.03未満となりますが、比重値が1.250を下回っている場合は、サルフェーションやセルの劣化・故障の可能性が考えられます。
また比重計でバッテリーを吸いだした際、正常なバッテリー液は無色透明ですが、液が茶色に濁っていれば電極(陽極板)が劣化、灰色に濁っていれば電極(陰極板)が劣化している可能性が考えられます。
※バッテリー液である希硫酸は危険な液体であり、 皮膚に接触すると重傷の薬傷を起こし、目に入れば失明することもあります。作業時は必ず手袋を装着し、同時に保護メガネの装着もしておくことが望ましいです。
「サルフェーション」とは?
上記のとおり、バッテリー放電時には鉛と硫酸が結合し硫酸鉛が生成されます。この硫酸鉛が結晶化したものをサルフェーションと呼びます。発生したばかりのサルフェーションはとても柔らかく、すぐに充電すれば電解液中に溶け込みます。しかしながら、バッテリーを長期間放置していたり、長期間充放電しながら使用すると、サルフェーションは次第に硬化して、化学変化しない状態(不活性)になります。正確に比重を測定するために

バッテリーの液量が減っている場合(水分だけ飛んでいる状態)では、硫酸濃度が濃くなりますので比重が上がり、バッテリー液を補充すると比重は下がります。そのため、比重を測定する際は、バッテリー液量が標準の状態で測定しましょう。
※補水は水道水ではなく必ず精製水を使用します。長い目でみると大幅コストダウンの精製水製造装置はこちら。
また、比重計が示す比重値はバッテリー液温によっても変化します。液温が上昇すると水分の体積が増加して硫酸密度が低下し、比重計の測定値は低く表示されます。逆に、液温が低下すると水分の体積が減少して、比重計の測定値は低く表示されます。
そのため、液温が常温から大きく変化している場合(寒冷地でバッテリー液温が低下している時や夏季のエンジンルームの熱でバッテリー液が上昇している時等)は、バッテリー液温が常温程度(20℃前後)になるまで待ってから測定するか、20℃からどれだけ液温が変化しているかを考慮して測定値を補正します。
補正値のやり方としては、液温が20℃よりも1℃上昇するごとに0.0007をプラスし、逆に1℃低下するごとに0.0007をマイナスします。 たとえば、液温が0℃のときに比重測定値が1.3だった場合は、1.3-0.0007×20=1.28となります。
液漏れに注意
精製水補水後の満水状態で 充電を実施しますと体積増加により溢れる可能性が高くなります。液漏れが起こるとバッテリー自体の寿命が減るのはもちろん、バッテリー外装部分に硫酸結晶(白又は青緑色の結晶)ができるため、腐食や端子部のケーブル断裂、バッテリー機能損傷が起こります。
硫酸結晶は毒性も高いため、バッテリー外部に硫酸結晶が見られた場合は、専用の中和剤を使って綺麗にしておきましょう。
バッテリーの交換時期

フォークリフトのバッテリーの寿命は、充電サイクルによって異なります。鉛蓄電池の寿命は約1,200〜1,500サイクル、年数では4〜5年が交換の目安です。
本来、JIS規格の高性能鉛バッテリーの電極板であれば、十分な耐久性があるとされます。電動フォークリフト用のバッテリーなら、使用環境によっては9年間使用できることもあるそうです。
鉛バッテリーの寿命は、使い方や種類によって変わってきますが、一般的に2~3年ごとにバッテリー交換することが推奨されています。
バッテリー比重が高い原因は満充電

バッテリーの比重が高くなるのは、バッテリー液の希硫酸濃度が高いことが原因です。バッテリーが満充電の状態であるため、バッテリーの劣化を促進してしまいます。
バッテリーの状態を正しく把握するためには、バッテリー比重を正しく測定し、数値だけではなく電圧、比重、CCA、始動時の電圧低下などもあわせて判断しましょう。
適切なメンテナンスを行うことが、長持ちさせる最大のポイントです。